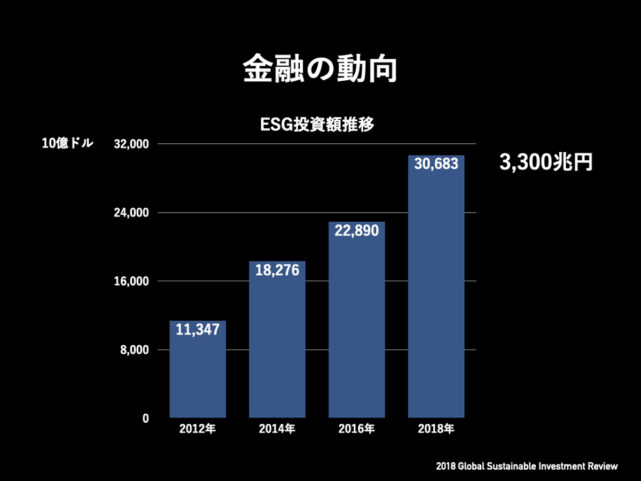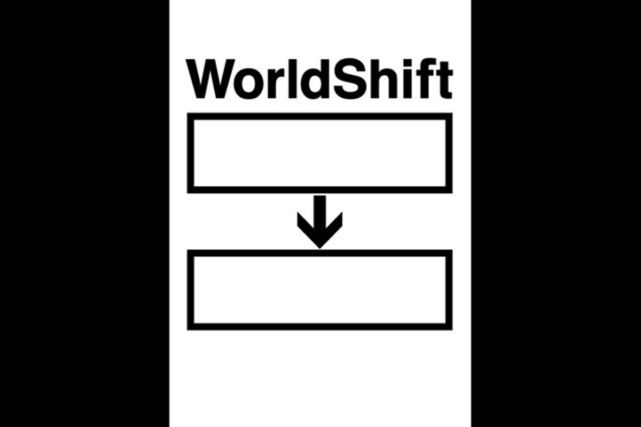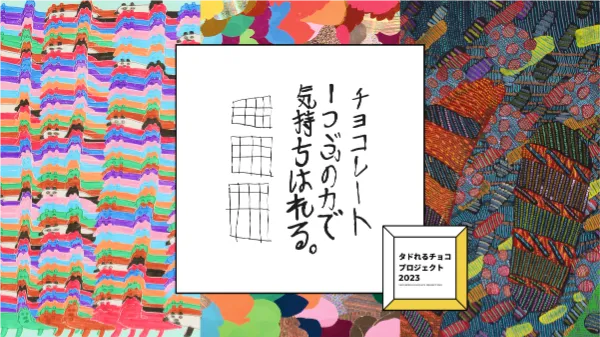【第2回】TOKYO油電力|大都会は油田である

写真・上2枚は、群馬県の天ぷら油発電所 (株アーブ)。下は、バイオ燃料プラントと染谷さん
日本では当然になり過ぎた大量生産、大量消費の次にある「大量廃棄」。海外での気付きを発端に、「環境問題解決をライフワークに」と帰国するも、生意気とされるばかり。
国内外のカルチャーショックに揉まれながら、「人は説得するよりも、共感してもらわないと何も変わらない」と考え、染谷さんの取り組みはより加速していきます。

自家製燃料を給油中

18歳の時に敢行したアジア放浪の旅。左はチベット、右はネパール、カトマンズの寺院での一枚
やっと抜けて村に辿り着くと、今通ってきた崖崩れの山の方からカランカランと音がします。周辺にいた山岳民族のような人々がみんな走って逃げるので、慌てて一緒に逃げました。ある程度ののところでみんなが止まり、山の方を一緒に振り返りました。すると、今通ってきた山からサーッ!と土砂が滑り、大きな岩がゴロンゴロンと木をなぎ倒して転がっていきました。
5分そこを通るのが遅かったら、あの土砂災害に巻き込まれていたに違いない。そこでへなへなと座り込んでしまいました。まだ18年しか生きていなくて、東京なんかで生きていると土砂災害で死にかけることなんてありませんから、本当に怖かった。
その日はその村に泊まりました。村の人がこれを「これはね、天災じゃない人災だ」という言葉が胸に刺さりました。どういう意味か、はじめはわかりませんでした。
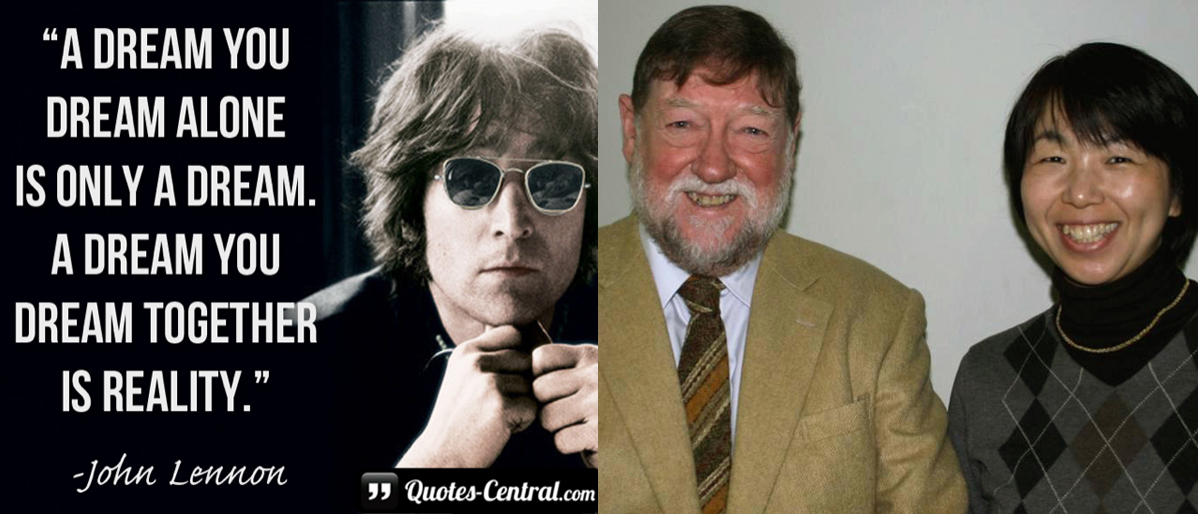
ジョン・レノンの言葉は「みんなの夢AWARD」でファイナリストに選ばれ、いただいた。C.W.ニコルさんとは、Earth Day東京実行委員会で
何百年間も、山岳民族の人々はそこで生活を営んできました。資源がないから木を切って薪にすることがあったとしても、山が崩れるほどの搾取はしないできたのです。それが、開発が進んでこうなったということでした。最近になって、日本でも土砂災害などの被害が頻繁に起きます。私は30年前に、今の日本の姿を見てしまったのだと思っています。
そこから先のカトマンズへの道のりも、足を滑らせたら流されてしまうような濁流の横を歩いたり、土砂で潰れた集落の上を歩いたり、それはそれは辛い行程でした。

お家にある油でロウソクができて、お湯が沸きます
大量生産、大量消費の次にあるのは「大量廃棄」です。私は、「環境問題解決をライフワークにする」と言って帰国するも、高卒女子では何もなく、「ただ生意気なことだけ言って」と、とらえられていました。
人は説得するよりも、共感してもらわないと何も変わらないと実感します。

左は明治学院大「ワンデーフォーアザース」で、自転車で墨田区の油を回収。右は東京ガスのキャンドルワークショップで、子どもたちに油のリサイクルをレクチャー
早過ぎたんです。いろいろなところでバカにされたり、お店ではマイ箸を使って断ったのに「割り箸持っていきなさい」ともらったりしました。当時私が箸を使わない理由を、その店のおばさんにはわからなかったんですね。
でもそんな経験から、わからない人にものを伝えるためのアプローチを考えるようになりました。
染谷商店に入れてもらったのは1991年。
それは「あ、ここだ!」と、気がついてしまっただけです。バブル期になおさら奇異な目で見られましたが、「環境問題解決の現場だ」ととらえていた私は、目をキラキラさせて現場仕事をしていました。しかし、今のような社会的評価もない中で、精神的にキツイこともありました。
その時、悩みながら見つけたものが「TOKYO油田」です。つまり、「東京という都市から油を掘ってるんだ」ということに気付いたんです。

Earth Day東京では、イベント来場者の油を回収して会場の電力を天ぷら発電。写真は「薬樹」ブースにて、薬樹の照井さんと

「肉フェス」、「ラジオinパーク野外イベント」でも、天ぷら発電や油回収をしてきました。発電自転車も活躍した

「目黒川みんなのイルミネーション2017」は、11月10日に点灯式を開催したばかり。今年は2.2kmの目黒川沿いを、地域の皆さまから集めた地産地消の天ぷら油燃料100パーセントでイルミネーションを灯します。2018年1月8日まで開催
最終回へ続く






 Saemi
Saemi 
 廣瀬あかね
廣瀬あかね